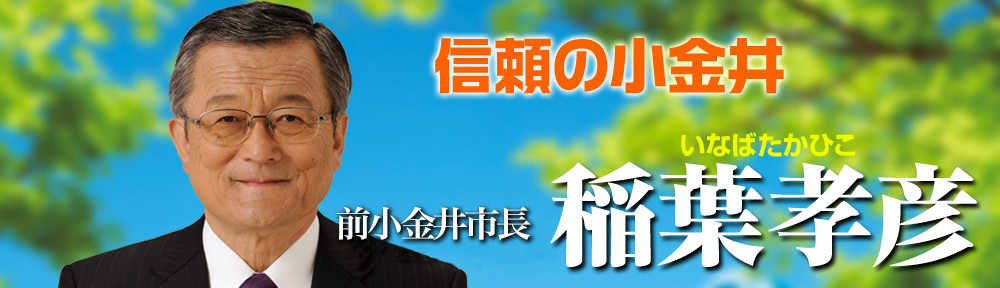不信任で議会解散そして辞職
昭和55年12月8日に開会した定例会は12日(金)佐野浩議員の一般質問「市民の血税の使途はこれでよいのか!」で、10月8日〜9日北海道釧路市で開かれた「全国都市問題会議」での星野平寿市長の公務出張の質疑で議会は大混乱に陥った。
これは、11月の決算委員会に出された「都市問題会議」の資料に基づき一部議員は入念な調査をしていた。
佐野議員は「いろいろ噂が飛び交っているが事実でなければ市長も迷惑であろうから確認します」と切り出し星野市長の会議の出欠席や、所在不明時の行動等を質した。質疑は答弁調査の休憩もあり延々と続き、15日(月)も日程変更し佐野議員の一般質問が続いた。さらに休会予定の16日も続いたが、本会議の開議宣告だけで会議は開けず空転のまま協議が行われ、午後3時すぎ星野市長が鹿野勇議長に「退職申出書」を提出した。これを受け17日を定例会最終日に繰上げ、各委員会を開催し補正予算等を即決した。最後に星野市長の辞職の挨拶があり午後5時前に大混乱の議会が終了した。
それが3日後の19日夕方、星野市長が突然議会事務局に「退職申出書の撤回届」を提出。自らの意思で辞職する場合、行政の混乱を避けるため、辞職は20日後になります。そのため撤回が認められ平常の形に戻った。
この一連の星野市長の動きはマスコミの好餌となり、市役所はテレビカメラや記者による取材合戦となり、年末・年始を通し連日報道番組や新聞で全国に混乱が報じられた。
同時期の昭和56年1月中旬「川上紀一千葉県知事が副知事時代の昭和49年春、知事選の選挙資金として都内の不動産業者から現金5千万円を受領した。その際『貴下の事業発展に全面的に協力するとともに、利権等についても相談に応じます』との署名入りの念書を入れた」と新聞が報じた。新聞やテレビの報道番組等マスコミは連日知事の念書問題と市長の北海道出張問題がセットで報道され、千葉県銚子市出身の私には辛い時期でした。
川上知事は「念書」を認め2月27日県議会で辞任が認められた。
2月4日、混乱する市政の中、議員の招集請求による異例の臨時会が開かれた。それは星野市長の不信任を決議するのが目的で、市長から一連の経過の釈明があり、これに全議員が質問する形になった。二転三転する答弁に複数の保守系与党議員からも「真実を話すように」との発言が出るのでした。質疑は日付を超えて続き、ついに市長は体調不良でダウン。回復には1週間との診断で17日に再開したが、市長は欠席のまま不信任案が上程され説明、質疑、討論後の採決で賛成24、反対2で可決された。
法により不信任が可決された場合、市長が辞任するか議会を解散するかを10日以内に決することになります。星野市長は2月26日に自らの辞任ではなく議会の解散を選択した。
それに伴う市議選が4月6日に行われ星野支持派は全滅となり、13日、新議員の初顔合わせが行われ、その後の全員協議会で「市長の即時退陣要求」を全議員の賛成で決めた。
4月19日星野市長は議会事務局長に「退職申出書」を提出し5月8日で市長を終えた。
5月31日に行われた市長選挙は3人が立候補し自民党の保立旻氏が当選を果した。
(つづく)