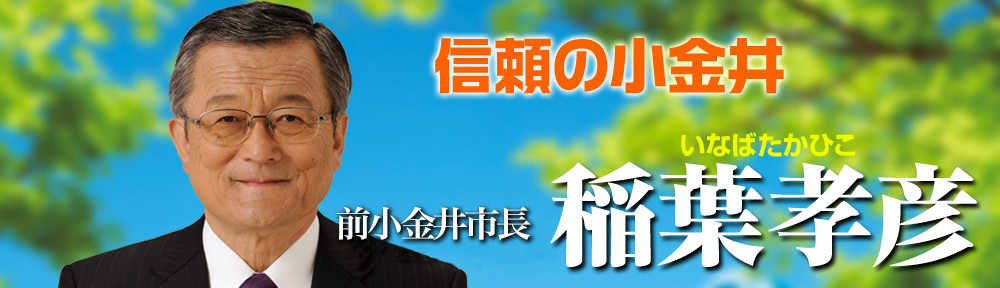最大の危機が財政再建を
30数年に渡る小金井市の財政危機は異常に多い人件費にあり、その原因は多すぎる職員と給与制度にあった。それは、全国ワーストの人件費比率や経常収支比率に表れていた。
平成9年度は定年退職する33人の職員の退職金の財源が無いことから東京では初めてとなる退職手当債(借金)を活用することになった。借金の許可に国と都は市の給与制度等の改正を条件とした。これには職員組合も飲まざるを得ず35年間小金井市を蝕み、地方公務員法にも反する同一年齢同一給(年齢給)にピリオドが打たれ「職務給」が導入された。
また、同時期に退職を願い出た2人の退職金が工面できないことから4月中旬まで有給休暇を使って在籍してもらい、新年度の予算から支払うという財政状況だった。
行財政改革を主張する議員は近隣市等と比較し200人以上の職員削減を主張していた。
財政計画から退職金が払えなくなる時が早晩くることから当局は6年頃から職員削減を打ち出していた。職員組合も財政が破綻した場合は自治権の放棄につながることから職員削減の協議に応じざるを得なかった。
7年(財)日本都市センターの専門家による「小金井市行政診断調査報告書」においても200人の職員が過剰であると報告された。
また、7年4月の市長選挙で大久保慎七市長は200人の職員削減を公約に三選を果した。
平成7年6月当局は197人の職員削減計画を組合に提案し、覚書を締結した。これは、7〜8年かけて完結させるというものでした。
当局は、給与制度の改正と職員削減を合わせて14年度までに51億5千万円の経費削減となると説明していた。
平成11年の市長選挙で私の公約はさらなる職員削減でした。当選後の記者会見で、私はさらに110人の削減を発表しました。
また、公約年金制度の改正により共済年金についても13年4月から年金の満額受給が65歳に引き上げられることから11年7月地方公務員法の改正があり、一般職の定年退職者が働く意欲と能力のある職員に改めて再任用として採用することで、新規採用はせず行革を進めることで組合とも合意した。再任用職員は職員定数に入りません。再任用制度は公務員優遇だとの意見が与党からも出て、議論は白熱したが与野党入り交じった採決で賛成12反対10で可決された。
この再任用制度の活用も行財政改革の後押しの力となった。
その結果、昭和50年前後の革新市政による常軌を逸した大量職員採用で、職員は1千130人。人件費比率は45・2%、金額は103億9千万円がワーストで、私の就任前の平成10年は892人で32・3%、98億8千万円だったが、27年の退任時は671人で16・2%、60億3千万円と大きく改善された。
私は昭和60年、小金井市の財政再建を果たすことを目的に市議会議員となり14年、そして市長として16年、議員や職員の身を切る協力、そして、市民のご理解でやっと他市並みとなり、最大の公約を果たしました。西の京都・東の小金井と評された職員組合も市の倒産を意味する財政再建団体への転落は自治権の放棄となり、国の監視下で財政再建に取り組むことになり、少しの金の使い道も制限されることから、自主再建の道に向けお互いに力を合わせた結果です。
(つづく)