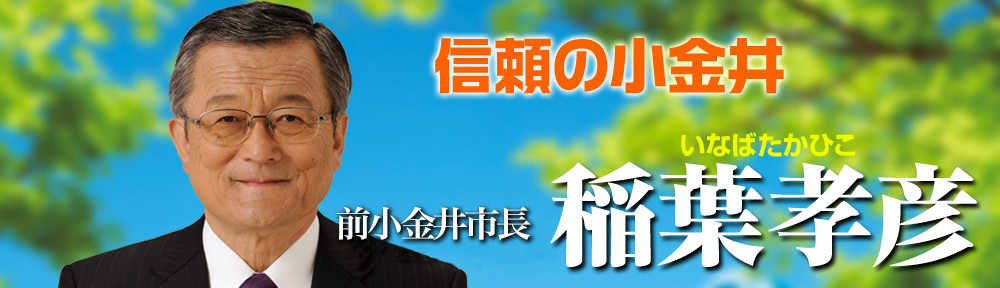市の病巣にメスが②
小金井市の最大の負の遺産は、長年の常軌を逸した職員組合の横暴とそれを許してきた当局の無力さである。それにより市民は取り返しのつかない財政的な損失を被ったのである。それは、文化、教育、運動施設の不足や街づくりの遅れ等に顕著に表れていた。
市役所内では仕事をしない組合員が幅を利かせ、真面目に仕事に取り組む職員が小さくなり肩身の狭い思いをしていた。この状況を打開するには組合の体質を変えることでした。その組合を支えていた病巣が維持補修係と施設管理係でした。
昭和58年6月、新たな施設警備の導入により任用換等の人事が発令され、この人事に不満の職員が当局を提訴した『丸井裁判』で組合の人事への介入が明らかになった。この裁判で証人として出廷した人事の所管である企画部人事課の部長も課長も関知していないと証言し、管理部長からは異動案がすでに作成されていて、そのまま執行するよう一職員から指示された、と証言した。組合に批判的な職員には本人が望まない職場に異動させることで職員をコントロールしていたのです。訴えは棄却されたが組合の介入が明らかになり、組合は分裂の兆候があらわになった。
昭和62年9月の定例会で大久保慎七市長から「学校施設の管理業務について」の市長報告があり激しい議論になりました。定例会最終日「学校施設管理に関する決議」が共産党を除く全議員の賛成で議決されました。
この決議の内容は①市民が納得できる管理方式を。②分散してる事務室を一か所に。というもので、私の悲願である財政健全化を進めるために必要な条件整備の内容でした。
私の主張の①は、機械警備で市内14校の学校警備は機械化すれば1校分の財源で済むのです。目指すのは公共施設の全ての機械警備です。②に関しては、施設管理係の係長は、天皇とも影の市長といわれるカリスマ的支配の組合執行委員長であり、仕事は本庁舎で宿直した職員からの報告や、駐車場管理の姿を見たこともなく、報告に要する一日の勤務時間は15分とのことであり、市民からも職員からも見えない個室での特別扱いを止めさせることでした。
この決議の内容が全く進展しないことで、私はこの実情をチラシや壁新聞、街宣車で「影の市長」を実名で批判しました。触れてはいけない所に手を入れたのです。覚悟の上ですが、駐車場にある私の車への悪戯や日付を超えての無言電話。注文しない25人前の寿司や蕎麦の出前。パトカーや救急車が我が家へ急行。私の自転車のカゴに詰めた新聞紙に火が付けられ警察の出動となる。遂に警察官が狭い我が家に張り込むことにもなった。犯人は特定できなかったが私の行動と一連の嫌がらせ時を同じくして起こったのです。
次の12月定例会の総務委員会で、私の「市議の市政ニュースに関して」が、翌年3月定例会では私と組合の絡みを大久保市長が組合に公文書で謝罪したことが議論になった。
時を経て、改革が進み、学校をはじめ公共施設は全て機械化され90人超の施設管理係は維持補修係40人と同様現在は正規職員ゼロになっています。
また、「影の市長」は異動されることもなく退職しました。
(つづく)